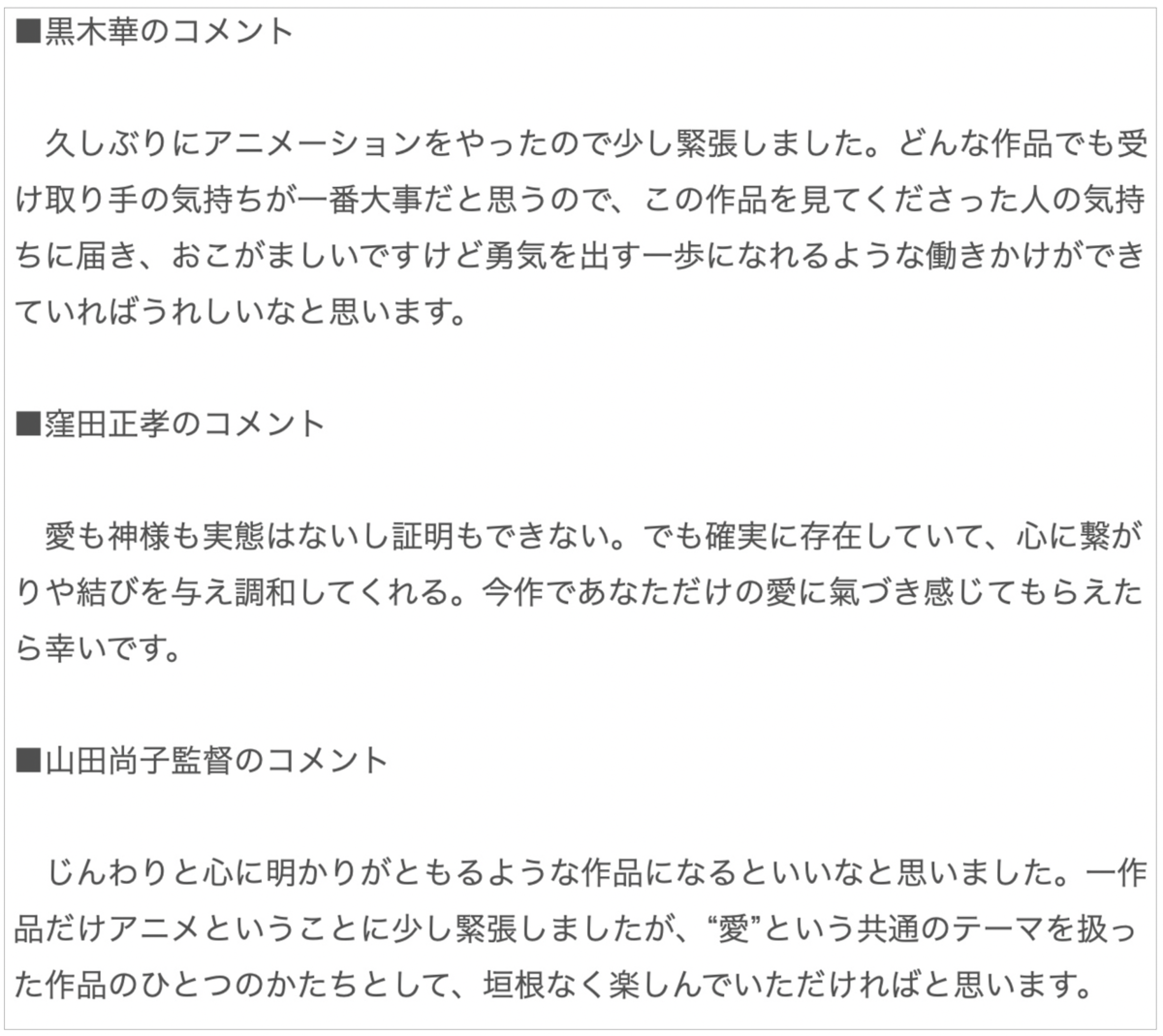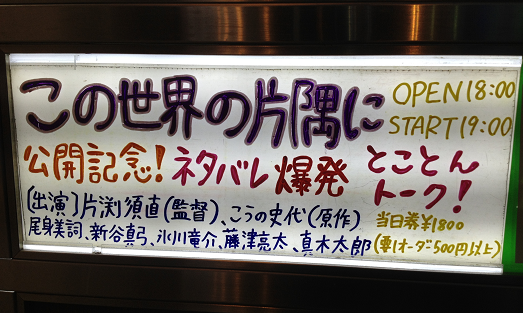宮﨑駿監督の『君たちはどう生きるか』の公開から1週間が経った。そろそろ踏み込んだ感想を書いてみようとTwitterで連ツイ用のドラフトを用意したものの、周知の通り、スタジオジブリおよび東宝の「宣伝なし」「広告なし」の戦略は今も続いており、内容について迂闊なことを呟けばどうしたってネタバレになりかねない。つまり書きたい感想をTwitterで呟くのは至難である(本日時点でもパンフレットの発売は未定となっている)。

自分の頭に湧き起こった想念を書き留めて、どこかにいるであろう同好の士がいずれ見かけることでもあればラッキーくらいの気持ちでSNSに放流するのが私のTwitterの流儀であるが、そもそも公式が世間に喧伝することを封じているような状態では感想を書き残すことも躊躇われる。
色々検討した結果、書き溜めた文章の「画像」を「センシティブな内容」としてTwitterに投稿し、Tweetを見る人の判断で表示/非表示を選択してもらうという方法を考えたが、うっかり設定のミスや想定外の事態(Twitterの突然の仕様変更など)があった時のリスクヘッジが取れないので、やはり本流に戻ってブログへ掲載することにした。
140文字で区切る必要がなくなったことから、元のドラフトの文章を全体的にまとめ直して大きく加筆・修正した。最初に書き殴った時のスピード感はそのまま活かすようにして、短文で区切る小気味良いリズムもできるだけ残すようにしている。初回の鑑賞後、1週間経過時点での感想はほぼ言い尽くしたと思う。妄想成分多めのまとまりのない駄文であるが、ご笑覧いただければ幸いである。
●
宮﨑駿監督の『君たちはどう生きるか』を観た第一印象は、極度に閉じたインナースペースで綺想が爆発している異形の怪作というものだった。首尾一貫する物語性も明確なメッセージ性も万人に向けた分かりやすい説明もかなぐり捨て、奔放に溢れ出す内的世界に身を委ねる愉悦に嬉々としているように見える。なんと自由なのかと思った。
分かりやすさと分かりにくさが未分化のままで同居しているように感じられるのも、いちいち小賢しい理屈や説明をつけず、ただ映像の奔流で語らせることに終始しているからだろう。作品が「分かる」ことにそれほどの価値はないし、むしろ分からないからこそ限りなく好奇心を触発される。そこには探求しても終わりのない永遠なる未知の領域が広がっている。そうしたものこそ開かれた作品であり、後述する『銀河鉄道の夜』や『不思議の国のアリス』などはその好例である。これらの作品を「分かる」人がどれだけいるというのだろう。「分かる」ことは作品の評価や価値とは無関係である。
とはいえ、『君たちはどう生きるか』には作品を読み解くためのアクセス・ポイントが幾つかある。
1つ目のポイントは「鳥」である。おびただしいほどの極彩色の鳥がスクリーンを舞う。しかしそれらはいずれも美しく愛すべき存在ではなく、糞便を撒き散らし平穏を脅かすおぞましくグロテスクなイメージに満ちた「鳥」だ。潜在意識下において「鳥」は、境界を易々と突き抜け、時には禁忌をも侵犯する表象となる。自由であると同時に安定を突き動かし、安心の土台を揺さぶるトリックスター。まるでこの作品そのものではないか。
中でもキービジュアルとして登場するアオサギは、『ファウスト』のメフィストフェレスのように主人公の少年を異界へ誘い出す。アオサギの手引きで少年は様々な世界を行き来し、そこで新たな人々や出来事と出会い、通過儀礼を経て、少しずつ大人へと成長してゆく。そういう意味でこの作品は、表面的な奔放さや精神分析的な難解さとは裏腹に正統的なジュブナイル作品としても成立している*1。
2つ目のポイントは「死」である。この作品では「死」が明確に描かれる。冒頭からいきなり母の死が描かれる訳だが、作品全体に通底するのは、『もののけ姫』のような生のリアリティを際立たせるために対置される死ではなく、むしろ絶対的な無の領域としての冷ややかな死者の世界だ。すでに『風立ちぬ』で表出していた気配であるが、本作ではそれが濃密に前景化している。
その印象もあって、個人的には『銀河鉄道の夜』を思い出す瞬間が何度もあった。あるいは『不思議の国のアリス』。ナツコの救出のくだりは、イザナギとイザナミ、オルフェウスとエウリディケの死と生を往還する冥界下り/現世回帰の神話的イメージが重なる。フェリーニの『8 1/2』の映像的記憶もうっすらと反響しているように思えてくる。主要キャストの少年は宮﨑駿、アオサギは鈴木敏夫、大伯父は高畑勲の3人の見立てであると捉えることもできる(少年は大伯父から何を受け継ぎ、何を拒絶したか)。
そして3つ目にして最大のポイントは「母」の存在である。軍需産業の活況で裕福な家に不自由なく育った主人公の少年は間違いなく宮﨑駿の自画像だ。そして少年の亡き母親のドッペルゲンガーのようなナツコは監督の実母の投影だろう。そう考えると、なぜ映画の時代背景が、吉野源三郎の小説「君たちはどう生きるか」が書かれた1937年(昭和12年)という日中戦争の始まった年ではなく、その少し後の時期であるのか、(あくまで想像でしかないが)朧げながら理解されてくる*2。
これまでの作中でもしばしば母の不在/喪失を描いてきた宮﨑駿は、老齢に至って自身のルーツに立ち帰り、自らの来し方、とりわけ母との関係性をあらためて見つめ直そうとしたのではないか。そして病弱だったという実母への監督自身の思慕とそこから遠ざけられる葛藤や確執というアンビバレンツに対して、自己セラピーのように作品を通してひとつの決着をつけようとしたのではないか。私にはそう思える。
ちなみに本作から宮崎駿の「崎」の一文字が「﨑」へと変わっていることにお気づきだろうか。考えすぎだと一笑に付されそうだが、私はここに監督の思いが込められているような気がしてならない。この作品がこれまでの作品とは性質の違うものであることを監督自身が宣言しているようにも見える*3。そして自身にとって今度こそ最後になると思われるこの長編映画が、キャリアのひとつの区切りとなるだけでなく、監督自身のこれまでの人生のわだかまりや拘りをも打ち破るものであったとしたら、そこにやはりクリエイターの業(ごう)を感じずにはいられない。人間が作品を作るだけでなく、作品が人間を作り変え、然るべき方向へ導いてゆく。

誰の指図も干渉も受けず、宮﨑駿にひとりの人間として描きたいことを描きたいように描かせ、やりたいことをやりたい放題やらせる。そのために巨額の広告宣伝費をすべて製作費に回し、製作委員会形式を取らずジブリ単体で興収の責務を負い、採算を度外視できる体制を整えた。Twitterでも指摘されていた通り、これは宮﨑駿の壮大な自主制作映画と言えるのかもしれない。初見時のTweetで私は「情報秘匿で始まったこの奇策が長期間に渡って効果を発揮するとは思えない。(中略)この作品にとってあまりにもったいない」と書いたが、最初から採算を主目的としない自主制作なら、確かにこの方法もありなのかもしれないと今は思う。もちろん宮﨑駿のネームバリューあっての奇策であるが。
しかしながら、この作品は7/14(金)の公開から17(月)までのたった4日間で、興収21億4,931万円という記録を叩き出した。『千と千尋の神隠し』の初動4日間興収を上回る大ヒット、『風立ちぬ』の初動150%のロケット・スタートだそうだ。「宣伝なし」は最大の宣伝効果を生んだ。あるいは宮﨑駿の神通力はまだまだ健在だったと見るべきか。
本作にはスタッフもキャストも、これ以上は望むべくもないスーパースター級の人々が一堂に会している。EDクレジットは壮観としか言いようがない。鈴木プロデューサーが用意した勇退の花道がこれだと思うと感慨深いし、一方で宮﨑駿は最後に自身のアーティスト・エゴを思いのままフィルムにぶちまけてみせた。こんな鋭い刃をまだ懐に潜ませていたのかと衝撃を受けた。
初めて観た日からすでに1週間が経過したというのに、いまだに幾つかの場面が脳裏にフラッシュバックし、それを反芻している自分がいる。こんな風に潜在意識を触発してくる肌触りは、個人的にはこれまでの宮﨑作品で経験したことがない。こんなザワザワした気分が後を引くことなどかつてなかった。
ビジュアルのアイデアはこれまでの作品からの使い回しと思われる部分が確かにあるし、その点に物足りなさや才能の枯渇を指摘する意見もある。しかし私には、そうであってもなお、今までの作品とは受ける印象が明らかに異なっているように感じられるのだ。まるで全編が主人公の少年の見た夢であり、私たちは作品の中に何ひとつ確かな現実感を抱けないまま、その夢を延々と見せられていたような気分に陥る。その狂った悪夢から醒めた後もまだ夢の中にいるような心地が続いている*4。
初見時は、宮﨑駿の最高傑作かといえば多分そうではないし、そんなつもりで作ってもいないだろうと思った。しかし今はその評価が少し変わってきている。これは宮﨑駿というクリエイター個人の枠組みをも超えてしまった、人間の普遍的な何か*5にまで触れてしまった、とんでもない作品なのかもしれない。作品を観ることで、その領域に触れてしまったからこそ、今も私は熱病の縁にいるような気分が続いているのだろう。この熱が醒めた頃にもう一度観て、初見で感じた様々な思いをあらためて確認してみようと思っている。
2023年7月21日 記
*1:構造的には『千と千尋の神隠し』に似ていると思う。
*2:映画『君たちはどう生きるか』は、同名の小説とは全く異なる内容のオリジナル作品である。映画の中では、主人公の少年が小説「君たちはどう生きるか」を読んで涙するというシーンがある。なお、宮﨑駿監督は1941年(昭和16年)の生まれなので、劇中の少年の年齢とは一致しない。
*3:もっとも、以前から監督がご自身の名字を記す際に、状況に応じて「﨑」の字を使っていることは多々確認されているので、これをもってただちに「新生 宮﨑駿」の誕生などと言うつもりはない。ただイラストや原稿への気軽なサインや、スタッフの一人としてのクレジットにおける恣意的な使い分けではなく、作品の監督名として公式に記載し、表看板として後世に残す以上、そこには何らかの自己主張と明確な意思が働いていることは間違いないと思う。
*4:この感覚は、もしかしたら漫画版の『風の谷のナウシカ』全巻を読み終えた直後の印象に一番近いのかもしれない。
*5:あえて言うなら神話性であり、あるいは深層心理やユング的な元型と呼んでも良い。