amazon prime videoのシリーズ企画ドラマ「モダンラブ・東京〜さまざまな愛の形〜」の第7話、山田尚子監督の『彼が奏でるふたりの調べ 』が2022年10月21日(金)から配信で公開されている。これは海外の連作ドラマシリーズ「モダンラブ」の舞台を東京に移した日本版で、荻上直子監督、山下敦弘監督、黒沢清監督など錚々たる映画監督が各話の制作を担当していることが話題になった。そして日本版だけのオリジナル企画として、日本の映像表現として今や欠かすことのできないアニメーションで1本制作することになり、そこで白羽の矢が立ったのが山田尚子監督だった。

興味深いのは、2022年3月30日の制作発表時においては、まだ山田尚子監督の名前がないことであり、一方、この時点ですでに全7話の構成が明らかになっていたことだ。
そして7月27日の続報で初めて山田監督がアニメーション作品で参加することが発表された。3月時点では第7話のスタッフもキャストも未確定(か、もしくはオープンにできなかった状況)で、その後、体制が固まり、7月27日の時点では完成していたと見るべきだろう。
山田尚子監督のフィルモグラフィーとしては、『平家物語』の後、キットカットのCM制作(現時点では2月と10月にそれぞれ春と秋の2ヴァージョンが公開されている)とほぼ同時期、6月のアヌシー映画祭で予告された『Garden of Remembrance』(2023年公開予定)の前の作品ということになる。おそらくキットカットのCMと『彼と奏でるふたりの調べ』とほぼ並行して制作されていたのではないかと思う。
特に『彼と奏でるふたりの調べ』は唐突に制作が発表され、『Garden of Remembrance』は比較的近い時期か、あるいはほとんど同時並行で制作公開まで日が浅かったこともあり、当初は制作会社もスタッフもまったく情報がなかったが、脚本はいつもの吉田玲子さんではなく、荻上直子監督*1が務め、制作会社は山田監督がキットカットのCMを監督した時のアンサー・スタジオが手がけること、またメインキャストが俳優の黒木華、窪田正孝であることまでは分かってきた。しかし、その他のキャラクターデザイン、作画監督、音楽などのスタッフについては全く未知のままで公開当日を迎えることになった。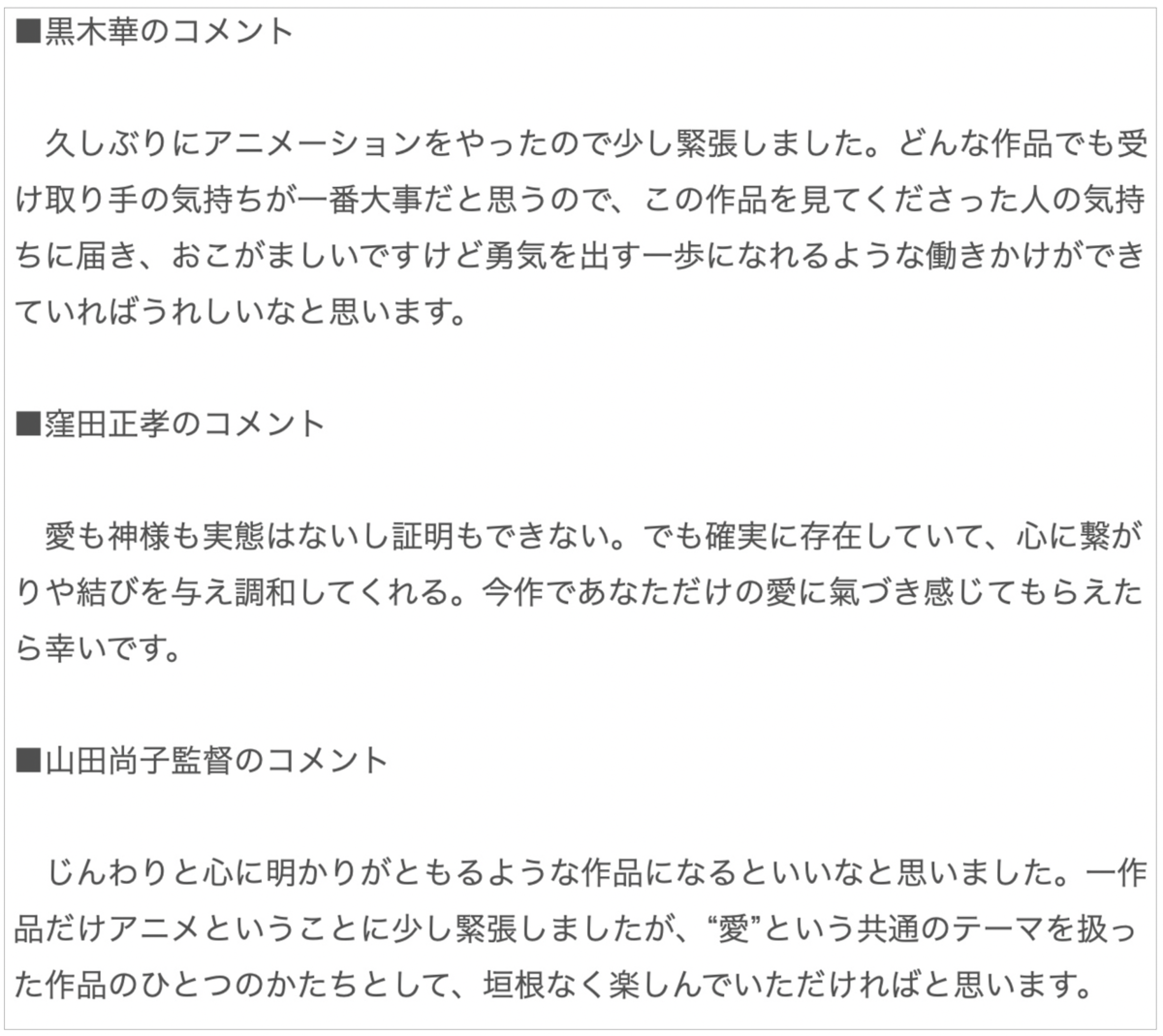
以下の文章は、公開翌日の10月22日(土)にTwitterへ投稿した文章をベースとしたもので、140文字の制限内では表現しきれなかった箇所を大幅に増補改訂している。また「モダンラブ・東京」が独占配信されているamazon prime videoは基本的に会員専用のサービスであること、あるいは後述するように、劇中で主人公の心の引き出しを開くことになる実際の楽曲の名前を一連のTweetで明らかにしてしまうと、これから観ようとしている人への重大なネタバレになると判断したこと…等の理由で公開を差し控えた情報が幾つかある。本稿ではそれらをすべて復活させている。従って作品を鑑賞済みという前提で記述するので、未見の方はprime videoで鑑賞の上でお読みいただきたい。
|概要
「モダンラブ・東京」シーズン1の第7話『彼が奏でるふたりの調べ』のamazonによる紹介文。
あらすじは上掲の画像に記載の通りであり、実はこれで物語のほとんど全部だ。あとは「その後、二人は再会する」と書けば完結してしまう。30分という短編の制約上、登場人物も物語もミニマムに絞っている。物語の筋を追うよりも、むしろその細部に描かれた表現にこそ注視すべきだろう。そういった意味で山田尚子監督の演出力が作品の成否を決める重要なポイントとなる。
主人公の珠美は「高校を卒業して14年」という台詞があるので、そこから察すると今は32歳くらいと思われる。社会に出て10年以上経っても、いまだ何者にもなれない自分の平凡さに嫌気を感じているどこにでもいる普通の女性である。
高校生の頃から自己卑下の傾向が強く、本人曰く「ヘタレ」。でも絵を描くことが好き。音楽が好き。表に出せない本心を笑ってごまかす癖があり、大人になってからはヤケのように酒を飲んでは失態を繰り返す日々。そんな無茶は20代でやめたものの、何者にもなれない焦燥感と不安は今も変わらず、今日も仕事でヘマをして、帰り道に馴染みのバーで酒を飲んで気分をまぎらわしていたその時、マスターが掛けたあるレコードに心の引き出しを開けられ、珠美の心は忘れていた高校時代の出来事へと戻っていく。そこにはピアノを弾く少年、凛の姿があった…。
『平家物語』を除けば、10代の少年少女主体の青春物語を紡いできた山田尚子監督にとって、30代の大人の女性を主人公として描くのは初めての試みである。もちろんこれまで大人を描いていなかった訳ではない。『けいおん!』シリーズでは大人の立ち位置から唯たちの姿を見守るさわ子先生がいたし、『たまこまーけっと』『たまこラブストーリー』ではたまこの父と祖父(と不在の母)、もち蔵の両親、そして商店街の面々がいた。『映画 聲の形』では将也と硝子のそれぞれの母親が強い存在感を放っていた。そこで描かれている「大人」は主人公たちの成長を見守り、彼らの自立を促す触媒のような位置付けにあった*2が、その「大人」自身は決して主役の座にはいなかった。
また、山田尚子監督がラブストーリーを真正面から描くのも実は『たまこラブストーリー』以来である。『けいおん!』シリーズに恋愛要素はないし、TVシリーズの『たまこまーけっと』ではたまこ自身の”ラブ”が描かれることはない。『映画 聲の形』の将也と硝子の関係はストレートな恋愛感情とはやや言い難く、『リズと青い鳥』は女性同士の関係であるが、すれ違って食い違う感情の交錯する行方を描くことにフォーカスされている。
そういう意味で「大人」の「ラブストーリー」は、山田尚子監督にとって意外にも新しいジャンルということになる(そもそも吉田玲子さんが関わらない脚本で作るのも初めてのことだ)。以前、監督は作品の中に自分自身を投影するようなことはないと仰っていたが、世代の近い珠美は、案外、山田監督の自画像に近いところがあるのではと邪推したくなる。
|感想
先程も触れた通り、本作は30分の短編である。しかし山田尚子監督のエッセンスが凝縮されているような作品だと思った。その感想をひとことで言うなら「愛おしい」。これに尽きる。高校時代の珠美も凛も初々しく愛らしい。心のときめきが表情と仕草だけで伝わってくる。大人になった珠美のダメさ加減も、むしろそこに人間くささと親近感を覚えてしまう。そんな風に世界を丸ごと肯定するような作り手のまなざしが優しい。この世界そのものが愛おしい。
少し驚いたのは『彼が奏でるふたりの調べ』には、山田尚子監督がこれまで手がけてきた諸作品の空気がそこかしこに感じられることだった。バーのカウンターにうつ伏せになる珠美の仕草は『けいおん!!』第26話(番外編『訪問!』)で風邪を引いてHTTのメンバーが見舞いに来た時のさわ子先生の姿を(心境は全然違うが)彷彿とさせるし、レコードプレーヤーとアナログレコードは『たまこまーけっと』の世界そのものだ。体育館の静寂は『たまこラブストーリー』、自転車に乗って一直線に駆ける姿は『映画 聲の形』、音楽室の光と空気感は『リズと青い鳥』といった具合。今回は監督が絵コンテをひとりで担当されているので、映像の特徴や音響の性癖まで包み隠さず表出されているように思う。またEDロールに「演出」のクレジット表記がない(演出助手の名があるのみ)ということは、それもご自身の仕事なのだろう。監督+絵コンテ+演出。この作品における山田尚子監督の純度は高い。
言葉にすればこぼれ落ちてしまうもの、言葉では言いあらわすのがもどかしい気配のようなもの、人と人との「間」に流れる空気、それらを掬い取る繊細な手つき…。山田尚子監督の個性として今や広く認識されるようになったそれらの映像表現のニュアンスは、30分の短編である本作においても如実に感じ取れる。確実にこれまでの作品を踏まえて、着実に表現を深化させている。山田監督は、キャラクターを記号的に消費させないようリアリティのある人間として描くことに注力し、人間の感情の本質的な部分にアニメーションでどこまで迫れるかをいつも求道的に模索している人なのだと思う。
珠美と凛の初々しくぎこちない、自分の中に芽生えた新しい感情に戸惑っているような遣り取りのなんと甘酸っぱく愛おしいことか。二人だけの静かな世界を共有する喜びと、静謐と沈黙を分かち合う描写のなんと優しいことか。私が山田尚子監督の作品に惹かれる要素の全てがこの短い作品の中に詰まっている。共に学校の中で居場所を見出せない二人を慈しむように包み込む優しい描写が胸に染みる。広い体育館に響くピアノの音も、冷ややかな廊下の静けさも、音楽室の柔らかな光も、二人だけの聖域のように美しい。そして瞳の揺らぎ、震える唇、ためらう指先、表情豊かな足元の動き。
山田監督の描く人物の背中姿はいつも忘れがたい印象を残す*3が、本作でも、取り返しのつかない喪失感に直面し、後悔にさいなまれる高校時代の珠美の背中姿が痛々しく、台詞も声も入っていないのに慟哭が伝わる仕草が切ない。台詞ではなく映像と音響がすべてを物語る。

この場面に台詞はない。音楽も環境音のようなアンビエント・ドローンが流れているだけだ。それでも珠美の仕草と表情だけで哀しいという情感が胸に迫ってくる。この一連のシーンのまるでミリ単位・秒単位で人の表情と行動の機微を捉え尽くした演出は、まさに山田尚子監督の真骨頂。
山田尚子監督は、音楽が沈黙よりもなお深い静寂を際立たせ、観る者の心の中に静寂を”響かせる”こと、無音の瞬間が観る者の意識の連続性を宙吊りにして、瞬間的に内的世界へ引きこむことを熟知している人だと思う。音楽を静寂のメタファーとして使い、無音の表現で観る者の意識を誘導する演出技法は、近年の作品においてますます先鋭化している。

『彼と奏でるふたりの調べ』では、この場面で”無音”が演出される。観る者の意識は物語の表層から一瞬切り離され、珠美の心の内部に引き込まれるような感覚を味わう。
本心を笑ってごまかす珠美の癖は、高校時代の凛との間に埋めようのない心の溝を作ってしまった。大人になった今、それはもうすっかり記憶の底に埋もれてしまって忘れ去っていた過去の出来事だったが、その思い出が蘇った瞬間、珠美の目から無意識のうちに涙が溢れ出すほど、彼女の心の奥底で今も深い傷となって残っていた。
その記憶を呼び起こすきっかけとなったものが、バーのマスターが掛けたレコード、シーナ&ザ・ロケッツの「ユー・メイ・ドリーム」だった。作品タイトルの『彼が奏でるふたりの調べ』は、高校時代の凛が体育館のピアノで珠美に弾いてみせたシーナ&ザ・ロケッツの幾つかのナンバーを指している。

直前まで近くで遊んでいたはずのバスケをやっていた生徒の声も姿もこの瞬間には消えている。珠美の主観の中ではもう凛のピアノしか聴こえていないのだろう。
|シーナ&ザ・ロケッツ/ユー・メイ・ドリーム
珠美の心の引き出しを開ける物語の重要な”鍵”となる「ユー・メイ・ドリーム」(You May Dream)は、1979年にリリースされたシーナ&ザ・ロケッツの大ヒット曲である。1980年頃、JALのテレビCMで頻繁に流れたので、シーナ&ザ・ロケッツを知らない人でも、今50代以上の方ならサビのリフレインに聴き覚えのある人も多いだろう。この選曲が脚本の荻上直子さんなのか、山田尚子監督の発案なのかはわからない。最初に作品のアイデア(このシリーズはすべて実話を基にしている)があって、そこに肉付けしていく過程で監督の意向が反映されたのだろうと推察しているが、今のところは不明だ。
劇中でバーのマスターがレコード・プレイヤーにドーナツ盤を載せた時、このアルファレコードのロゴマークが目についた*4。

バーのマスターがおもむろにかけたドーナツ盤。拡大して見るとラベルに「YOU MAY DREAM」と書かれている。
一瞬「?」と思っていると、すぐにギターのカッティングが聴こえてきて「あ、これはたしか…」と思った直後、”あなたの事思うと…”と歌声が聴こえてきた。その時、朧ろだった像が急に焦点を結んで、私は思わず「ああ」と声を出していた。高校生の珠美と同じように「シーナだ」と呟いていた。さすがに涙を落としたりはしなかったが、彼女が高校生の頃の記憶を次々にフラッシュバックさせるのと同様、私もまた過去の思い出や当時の空気がまざまざと脳裏に蘇ってきて冷静でいられなくなった。なぜなら「ユー・メイ・ドリーム」は、私が10代の頃にリアルタイムでヒットしていた曲だからだ(正確には中学3年生の頃)。
劇中で珠美が語る「音楽は心の引き出しみたいなところがあって、ふとしたきっかけで過去の記憶が全部溢れ出してしまうことがある」を自分もまた身でもって体験することになった。長く聴くことのなかったこの曲を”ふとしたきっかけ”で耳にして、記憶を過去に引き戻されて心をかき乱されてしまった。劇中の主人公と同じ体験を同じタイミングでシンクロしたかのように味わうという、なかなか起こりえない稀有な出来事だったと思う。もっともこちらは珠美の3倍くらい昔の記憶だけれど。
体育館のピアノで凛が奏でるシーナ&ザ・ロケッツのナンバーの曲名を珠美が事もなげに当ててみせる”Radio Junk”も”Lazy Crazy Blues”も、”You May Dream”と共にアルバム「真空パック」(1979年)に収録されている楽曲である。細野晴臣がプロデュースしたこのアルバムはYMO一派が制作に関わった、60年代のガールズ・ポップとテクノポップとパンク/ニューウェイヴの要素が渾然一体となった傑作である。
「真空パック」は制作時期や背景から考えると、鮎川誠がギターで客演したYMOの「ソリッド・ステイト・サヴァイヴァー」のある意味で兄弟アルバムと言えるが、パンク/ニューウェイヴ/テクノ色にとどまらず、イギー・ポップ率いるザ・ストゥージズの”1970”に日本語オリジナル歌詞をつけた”Omaega Hoshii”、キンクスの”You Really Got Me”の轟音カバー、ジェームズ・ブラウンのパンク解釈など、古典に対するアプローチも光る。グラビアから出てきたのかと思うほどフォトジェニックなシーナと鮎川誠のルックス、キッチュでキュートでいながらタフでタイトな音作りなど、時代的にはB-52’sの1stからの影響もあったのではないかと思う。

(左)シーナ&ザ・ロケッツのアルバム「真空パック」(1979)のジャケット。
(右)アナログ盤のラベル。「Produced by Harry HOSONO」(細野晴臣)と記されている。
シーナ&ザ・ロケッツ ー “You May Dream”
細野晴臣が作曲に関わっており、YMOのメンバーも全面的に演奏をサポートしているシーナ&ザ・ロケッツの出世作。
シーナ&ザ・ロケッツ ー “Radio Junk”
YMOがライブアルバム「Public Pressure」(1980年)でカバーしており、作曲も高橋幸宏なので、YMOのオリジナルと思っている人も多いだろうが、元はシーナ&ザ・ロケッツのために作られた曲。なお、YMOバージョンはライブ音源しか残されていない。
シーナ&ザ・ロケッツ ー “Lazy Crazy Blues”
”You May Dream”のシングル盤(アナログ45回転のドーナツ盤)のB面収録曲だった。
この時期(アルファレコード在籍時)のシーナ&ザ・ロケッツは、サンディー&ザ・サンセッツと同様にYMOファミリーだった。同時期のスネークマンショーの1stアルバム(通称「急いで口で吸え」)に「レモンティー」で参加しているのもその縁である。*5
シーナ&ザ・ロケッツ ー “レモンティー”
スネークマンショーの1stアルバムに収録されたこのバージョンが最高という人は多い。私もそう思う。
70年代までブルースロックのサンハウスにいた鮎川誠の新しいバンドが、テクノポップのYMOのメンバーによる全面的なサポートの元にアルバムを発表し、一方で鮎川誠がYMOの「ソリッド・ステイト・サヴァイヴァー」のタイトル曲と”Day Triipper”でギターを弾くというのは何とも不思議な感じがするが、同じ頃、四人囃子の佐久間正英がプラスチックスに加入し、プログレのマンドレイクで活動していた平沢進がテクノパンクのP-MODELを始めるといったような、ジャンルの垣根を越境した活動が次々と起こり始めた時期だった。
それが1979〜1981年頃という時代の境目の光景であり、その背景には70年代半ばに勃興したパンク・ロックと、その後に続いたニューウェイヴ・シーンがもたらした音楽的活況があった。停滞した音楽シーンが世界的規模で急激に地殻変動を起こし始めたような空気がそこにあった。その中からシーナ&ザ・ロケッツは登場したのだ。
高校卒業から14年ということは、珠美と凛の出会いは2008年頃だろうか。ちょうどシーナ&ザ・ロケッツが活動30周年を迎えた年だ。その頃の高校生でシーナ&ザ・ロケッツ好きというのはなかなか珍しいと思う。好きな音楽が同じ者同士は何をしなくても分かりあえるというのは私も実感するところなので、シナロケ好きの二人(まして同好の士は周りに誰ひとりいなかったろう)が、すぐに意気投合したのはとてもよくわかる。好きなものが同じというだけで人はつながり合える。*6
|花・鳥・飛行機・空
山田尚子監督はこれまでの作品の中で、路傍で可憐に咲く花や、空を舞う鳥や、頭上を飛んでいく飛行機(および飛行機雲)や、吸い込まれそうなほどに広い空を繰り返し描いてきた。『彼が奏でるふたりの調べ』でも、ひまわりの花束、学校をエスケープした二人のベンチの側に咲く花、足元から飛び立つ鳥、太陽をかすめる飛行機、珠美の視線の向こうに一直線に伸びる飛行機雲、二人乗りの自転車の背後に広がる青空などが印象的に描かれる。*7



『彼と奏でるふたりの調べ』より。
山田監督の描くこれらの映像言語は、人間の営為とは無関係に世界は超然と存在し、人の思惑とは関わりなしに、美しく自由にそこにあることを物語っている。物語の登場人物が他者との関わりに悩み苦しみ、地べたを這いずり回るように四苦八苦し、時には互いに争い合い、哀しみの底に突き落とされても、それでも世界は美しい。
『映画 聲の形』の公開後、山田尚子監督はインタビューでこのようなことを語っている。
「この子たちは明日を生きるのも辛そうなくらいすごく悩んでいますよね。でも一歩引いて見た時に、その子たちがいる世界ごとはそんなに絶望感がある訳じゃない。ちゃんと生命は宿っていてお花は咲くし、水も湧くし。彼らがいる世界全てが悩んでいたら嫌だというか、彼らがパッと見上げた空は絶対に綺麗であって欲しいと思ったんです」
それは物語の世界を外から眺める俯瞰的な視線を感じさせるもので、物語内の世界と登場人物の行く末を静かに見守る”神の目線”のようでもある。
|ジョン・カーニー監督と山田尚子監督
オリジナルである「モダンラブ」は、ニューヨーク・タイムズ紙のコラム「Modern Love」に投稿されたさまざまなエピソードを元に制作されたamazon配信のドラマ・シリーズだ。「モダンラブ・東京」はその日本版で、オリジナル「モダンラヴ」で製作総指揮・監督・脚本を務めたジョン・カーニー(John Carney)の名前がオープニング映像にExecutive Producerとしてクレジットされている。
ジョン・カーニーは『ONCE ダブリンの街角で』『はじまりのうた』『シング・ストリート 未来へのうた』などの作品で知られるアイルランド出身の映画監督である。オリジナル「モダンラブ」が、日本での配信時には「モダンラブ 〜今日もNYの街角で〜」とサブタイトルがついていたのも、ジョン・カーニーに敬意を表してのものだろう。そのジョン・カーニーが「モダンラブ・東京」の製作にも関わっている。この事実は『彼が奏でるふたりの調べ』の制作にあたって、山田尚子監督に何らかの大きな心理的影響を及ぼしていたことを想像させる。
かつて京都アニメーションのスタッフ・ブログで山田尚子監督は、ジョン・カーニー監督の『シング・ストリート』などに触れて、彼の描く世界が好きだと率直に語っていたことがあった。また『リズと青い鳥』公開時のインタビュー(2018年3月)では、HomecomingsのED曲のデモ音源を聴いた時の印象として、「ジョン・カーニー監督の映画の中の世界に入ってしまったような気分でした。良いも悪いもない。ただもう、これなんだ!って思いました。わかりやすくいうと、感動しました」との発言を残している。
そのHomecomingsへのインタビュー(2018年5月)でも、ギターの福富優樹さんが「打ち合わせ段階でも『シング・ストリート』の名前は挙がってた気がする」と語っている。
自身もかつてはミュージシャンだったジョン・カーニー監督の作品は、いつも音楽と人との関わりを描くという特徴があり、その世界はどれも多幸感に溢れている。そう、どこか山田尚子監督が志向する作品世界と似通ったところがあるのだ。山田監督にとって憧れの映画監督の一人であることは間違いないだろう。そのジョン・カーニー総指揮のシリーズで制作を任されるという栄誉。そのことを山田尚子監督が意識していなかったはずがない。静かに気合が入っていたのではないかと想像する。『彼と奏でるふたりの調べ』もまた「音楽がつなぐ人の想い」のドラマであり、まるでジョン・カーニー監督へのオマージュのように思える。
|スタッフ情報
『彼と奏でるふたりの調べ』は、キットカットのCMと同じアンサー・スタジオの制作。脚本:荻上直子、絵コンテ:山田尚子、キャラクターデザイン/作画監督:林佳織、音響監督:木村絵理子、音楽:パソコン音楽クラブという布陣となっている。原画には『平家物語』でキャラクターデザイン/総作画監督を務めた小島崇史さんの名前もある。
音楽を務めたパソコン音楽クラブは数年前にTwitterのフォロワーさんに教えてもらって以来、ずっと注目して聴いてきたテクノユニットだが、つい先日もサイエンスSARU制作のTVシリーズ『ユーレイデコ』でEDテーマ曲を担当していたばかりだった。サイエンスSARUは、山田尚子監督の『平家物語』、次回作『Garden of Remembrance』の制作会社であるが、ここでも監督と間接的につながっている。
山田監督とは初仕事となったパソコン音楽クラブの劇伴は、彼らの独自性を発揮するものではなく、監督がこれまでの作品で確立させた"静謐と沈黙"という「山田尚子印」の世界観を壊さないように配慮しているという印象を受けた。中盤のアンビエント色の強いサウンドは、牛尾憲輔さんの劇伴へのリスペクトのようにも感じるのだが、実際のところはどうなのだろう。
それにしても、シーナ&ザ・ロケッツとパソコン音楽クラブが山田尚子監督を介して出逢うとは…。この予期せぬ邂逅の驚きは大きかった。やはりこの2組のアーティストの選択は監督ご本人からのオファーだったとしか思えない。
|補遺
以下、上述の各章には収められなかった、もしくは収める場所がなくて漏れてしまった小ネタ的なものを覚え書きとして列挙しておこうと思う。
■珠美の描くイラストは山田尚子監督ご本人の直筆だろうと思う。

■音楽がこじ開けたのは過去の恋の記憶だけでなく、自分の夢や本当にやりたかったことを思い出すことでもあった。そしてここでも「大人」である美術室の先生の言葉が、時を越えて珠美の背中を後押ししている。
■この作品に単独の「キービジュアル」がないというのは、シリーズ作品の一編なので仕方ないとは思うが、ちょっと惜しい気がする。
■オムニバス連作の中の一編ということで、この作品に関する山田監督のコメントは制作発表時点の短い発言しかなく、もっと踏み込んだインタビューを期待したいが、なかなか難しそうだ。
■EDロールにシーナ&ザ・ロケッツの楽曲使用のクレジットがないのは、何か事情でもあるのだろうか。
■ひまわりの花言葉は花の数によって異なるらしい。花が五輪の場合の花言葉は「ない」そうだが、六輪になると「あなたに夢中」という意味を持つらしい。ラストで珠美と凛の持つひまわりの花束はどちらも六輪だ。
■またラストでマスターが撮影する二人の写真は、背景の調度品がいい感じに重なって背中に羽根が生えたように見える。今あるところからほんの少し飛び立てるような気持ちのあらわれであると同時に、二人で一つになることで飛ぶことのできる天使の羽根のようでもある。
|終わりに
『彼が奏でるふたりの調べ』は、観終わった後、心の奥に優しく暖かな灯が点るような愛らしい作品だった。何者にもなれなくていい。自分を卑下することはない。あなたはあなたであるというだけで価値がある。もしなりたい自分があるなら、そこから一歩踏み出すための勇気が1mmあればいい。この作品には生きることに不器用な大人たちへ贈るエールが込められている。過去の痛みを克服して今、1mmだけの勇気を持って前へ進む。その描かれ方が優しく暖かい。
今回も山田尚子監督に最大級の称賛と感謝の想いを贈りたい。これからも折に触れて見返すことになるだろうと思う。小さくて愛しくてチャーミングでキュート。印象的な場面も多く、それらは端正で絵画的で空気の質感まで織り込んだように美しい。素敵な作品だった。大好きだ。
|そして『Garden of Remembrance』へ
この原稿を執筆中に続報が入ってきたので、最後に最新の動向について触れておきたい。スコットランドで開催されている英国唯一の日本のアニメーション・フェスティバル「Scotland Loves Animation 2022」において、現地時間の10月28日(金)17:50から(日本時間は10月29日(土)深夜1:50〜)、エディンバラにあるCameo Picturehouseで山田尚子監督の新作『Garden of Remembrance』のワールドプレミア上映がおこなわれた。6月のアヌシー映画祭での告知通り15分の短編作品。上映後、山田監督が登壇され、約1時間のQ&Aセッションが行われた。非常に盛況であったことが窺える。
キービジュアルのポスターには、新たに”A short film by Naoko Yamada”の一文が追記されている。とてもパーソナルな作品という印象を受ける。15分の短編はこれまで山田監督が手がけてきた商業作品とは明らかに性質の違うものだ。インディペンデントのアニメーション作家の作品のような、あるいは名の知れた商業映画の監督が自分自身のアーティスト・エゴを叶えるために撮った実験映像のフィルムのような、そんな作品を想像してしまう(スタッフも最小限の人数に絞ったのではないだろうか)。いよいよ本当の意味で山田尚子というクリエイターがその作家性を明らかにする機会がやって来たのではないかと思う。

現地で観た人の感想が少しずつTwitterで流れてくるのをウォッチしていたが、『Garden of Remembrance』はその言葉通り*8、亡き者への「追憶の庭」であり、死と喪失、そしてグリーフワーク*9が大きなテーマになっていると思われる。幾つかの監督の発言を綜合すると、この作品もまた音楽が主軸にあり、「音楽とアニメーションのコラボレーションを考えるところから始まった」らしい(コミックナタリー 2022年10月29日記事参照。以下にリンクあり)。
本作で山田さんは「監督・脚本」の双方でクレジットされている。「台詞のない映像と音楽だけの作品」であるという情報も入ってきた。実験的で非常にチャレンジングな作品のように思える。
日本語訳「山田尚子監督の『Garden of Remembrance 』は、生と喪失をテーマにした素晴らしい短編作品で、私たちは幸運にも#SLA22 で観ることができた」 https://t.co/Yh8nyK1Kaa
— エンドス (@los_endos_) 2022年10月29日
日本語訳「山田尚子監督の15分の短編はとても素晴らしく、彼女は死、時間の経過、そして愛する人がいなくなった時に前へ進むための方法について語った。10回観ないとわからないような細かいニュアンスに溢れている。山田監督にサイエンスSARUの空気を加えたようだ。彼女は世代を超えた才能の持ち主だ」 https://t.co/v2Z4VxrXrc
— エンドス (@los_endos_) 2022年10月29日
【イベントレポート】「Garden of Remembrance」山田尚子監督が制作秘話語る、キャラクター原案資料も公開https://t.co/FFLtLEIzbu pic.twitter.com/soYm6QdVam
— コミックナタリー (@comic_natalie) 2022年10月29日
Our Animation Education Day returned this year with some fantastic masterclasses from Naoko Yamada, Eunyoung Choi and Jack Liang - so happy to be back at the Edinburgh College of Art ✨ Can't wait to be back next year! pic.twitter.com/pfYM1dDtSf
— Scotland Loves Anime (@lovesanimation) 2022年10月29日
昨年の後半からかつてないペースで新作を発表し続けている山田尚子監督。商業性と作家性の双方を発揮できる状況になった今、まさに充実期に入ったといっても過言ではないだろう。『Garden of Remembrance』は短編とはいえ(いや、商業性にとらわれない短編だからこそ)、監督のキャリアの中で後になって幾度も参照される重要なマイルストーンになるような予感がする。
『Garden of Remembrance』は2023年公開の予定。今から待ちきれない。
2022年10月30日 記
*1:映画『かもめ食堂』『めがね』『彼らが本気で編む時は、』など代表作多数。
*2:エディプス・コンプレックス的な障壁でない点には注意が必要かと思う。
*3:『映画 聲の形』の硝子は特にその印象が強い。
*4:このバーのマスターは間違いなくリアルタイムでこの曲を聴いていた世代のはず。
*5:シーナ&ザ・ロケッツの「レモンティー」も彼らの最初期の代表曲であるが、これはヤードバーズの”Train Kept a Rollin’”に日本語オリジナル歌詞を載せたもので、元々は鮎川誠が在籍したサンハウスの楽曲のセルフカバーだ。ベースラインのドライブ感が最高なこの曲は、1951年発表のTiny Bradshawの楽曲がオリジナルで、その後、Johnny Burnette(1956年)、ヤードバーズ(1965年)と順にカバーされて有名になった。元々は「ニュー・ヤードバーズ」だった初期のレッド・ツェッペリンもステージで度々取り上げ、1974年にはエアロスミスもカバーしている。この時期以降のカバーはどれもヤードバーズを範としていると言ってよく、それほどまでにヤードバーズのポール・サミュエル=スミスが編み出したベースラインは天才的なものだった。ちなみに英国3大ギタリストが在籍していたことで知られるヤードバーズのこの時期のギターはジェフ・ベックで、”Train Kept a Rollin’”のギターもベックが弾いている。日本語オリジナル歌詞は過剰なまでにエロティックな隠喩に満ちているが、そもそも原曲の歌詞が性的隠喩を含んだものなので解釈としては間違っていない。
*6:余談であるが、アニメーションの『けいおん!』シリーズのキャラクターの名前が、3年2組のサブキャラクターも含めて1980年代前半の日本のパンク/ニューウェイヴ・シーンのミュージシャンから多く引用されていることはよく知られているが、不思議なことにP-MODELやプラスチックスやヒカシューや一風堂と同時期に登場したシーナ&ザ・ロケッツのメンバーからはひとりも選ばれていない。鮎川、奈良、川嶋という苗字を持つキャラクターがいないのは今思うとちょっと意外に思える。
*7:「鳥」については、山田尚子監督の前作『平家物語』ではとりわけ重要な意味を担っており、戦い合って儚く散る人の生命とは対照的に、自由で優雅に空を舞う存在として、またある時は人を脅かす不吉な存在として描かれていた。それは「生」と「死」の両義性を孕むと共に、人間にとっては理不尽な自然界の象徴のようでもある。
*8:"Garden of Remembrance"は通常の庭や公園ではなくメモリアル・ガーデン、つまり亡き人を偲ぶための追悼の庭園、もしくは直截的に霊園を意味しており、"Garden of Remembrance"という名の庭園や霊園は世界各地に実在する。なお作品のタイトルが、”a”や”the”のない無冠詞であることには注意が必要だろう。一般的な庭でも、特定の庭でもない、もっと抽象的な「追悼の庭」「追憶の庭」という概念を指しているように思える。
*9:親しい人との死別や離別によってもたらされた悲嘆から立ち直るためのプロセスのこと。